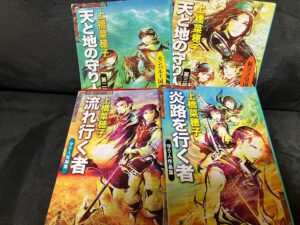今年に入っても、インフルエンザや溶連菌などの感染症の勢いは多少減っているものの、全国的に警戒レベルのまま。22日に大寒を迎えましたが、春のような陽気の日もあったり、来週からまた寒くなるようで・・・不思議な冬です。
最近、千葉では”鳥インフルエンザ”によるニワトリの殺処分や卵の価格高騰などのニュースもよく流れています。
ここ数年でよく耳にするようになった”鳥インフルエンザ”。なぜこんなに話題になるのか、よく分からずにニュースを見聞きしているので、調べてみることにしました。
※厚生労働省のHPより情報を抜粋※
・鳥インフルエンザとは?・
→A型インフルインザウイルが引き起こす鳥の病気のこと。高病原性・低病原性に区別されます。
H5N1:1997年香港で鳥ーヒト間の感染が確認。2003年から東南アジアを中心に各地で報告。海外では家族間などの濃厚接触での報告はあるようです。治療薬→タミフルを検討
H7N9:2013年中国で鳥ーヒト間の感染が確認。治療薬→タミフルを検討
どちらも日本での持続的感染の報告はなし。ただし、野鳥や感染した鳥との濃厚接触による感染疑いがあるようでしたが、感染したとの断定的な報告ではありません。日本の感染症分類ではどちらの型も2類感染症に分類されています。(結核と同じ分類。)
ちなみに、新型インフルエンザと鳥インフルエンザを混同しがちですが、全く違います。どのインフルエンザの型でも、ヒト―ヒト間での持続的感染が起こるようになった場合に、新型インフルエンザの分類に移行します。今はヒトーヒト感染にならないよう水際で戦っている状況です。
確かに、新型インフルエンザに移行してしまうと、免疫がないため広がりも早そうでちょっと心配。そのため、大々的なニュースになり、厚生労働省を始め、環境省や農林水産省、国立感染症研究所などで詳しい情報が掲載されているのです。
インフルエンザウイルスは熱に弱いので、加熱すると感染性はなくなりますが、感染が他の地域に広がらないようにニワトリの殺処分が行われます。そのため、相対的に鶏卵は少なくなり、高値の花になりつつある卵。
その鶏卵は生薬名で、”鶏子黄(ケイシオウ)”と言われます。処方では傷寒論にある「黄連阿膠湯」の構成生薬ですが、製剤化している商品には含まれていません。(アレルギーの問題や保存・加工が大変なのかもしれません。)
・鶏子黄・

中国の文献では、衰弱や過労による吐血、吐き気、やけどや湿疹に用いられていました。卵黄を火にかけて油を抽出した”卵黄油”は内服の他にも、外用剤として用いられたようです。日本でも民間薬として、血液循環の改善や自律神経に働きかける効果を期待して古くから使われています。
Amazonで”卵黄油”と検索すると色々な商品が出てきます。2000円くらいなので、ご興味のある方は検索してみてください。
鶏子黄は阿膠(ニカワのこと)と同じ効果があると言われているため、黄連阿膠湯の構成生薬に両方入ることによって相乗・相加効果を期待しているのだと思います。
・鶏子殻(ケイシカク)・

カルシウムやマグネシウムが主成分。消化性胃痛や反胃(もたれ感・むかつき)に、胃酸中和や粘膜保護を目的に使われます。また、小児の栄養不良やくる病(ビタミンⅮ欠乏症)にも使われた記録があります。
卵は、動物性たんぱく質を摂る機会が少なかった昭和の半ばまで虚弱体質や病後の回復に栄養価の高い物として食べられてきました。当時は、バナナと同じく高価なものだったようです。
現代では、動物性たんぱく質は簡単に手に入るようになり、栄養事情も良くなったので積極的に卵を食べる必要性は少ないだろう。という文献を見て、妙に納得してしまいました。健康な人が1日に何個も食べてもいいっていうのは・・・栄養学的に考えると過剰にならないのだろうか?なんて、考えてしまったり。
でも、たまごサンドって美味しいですよね。

書いていくうちに食べたくなり、ご近所”日暮らしサンドウィッチ”さんの厚焼き玉子サンドを。厚焼きタイプは初めてでしたが、出汁とからしマヨがよく合ってボリュームもあり満足でした。たまごサンドの食べ比べも面白そうです。ただし、食べすぎ注意です!
日暮らしサンドウィッチ → https://www.jamtreejammin.com/higurashi-sandwich
M