明日から彼岸入り。ようやく、秋の気配を感じられるような朝晩になってきました。9月の半ばまでこんなに暑さが続くとは思いませんでした。外出気にもならず、エアコンの下で読書時間が長かった8月でした。
・鞄に本だけつめこんで 群 ようこ
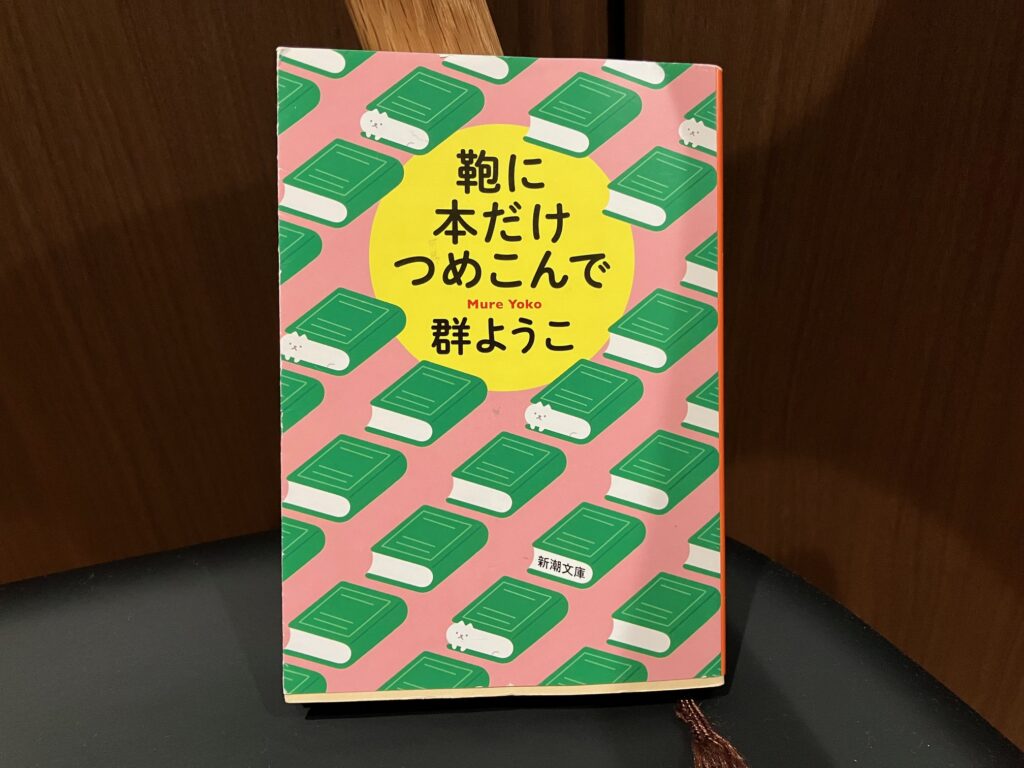
24冊の本の紹介とともに、それぞれの本に関連した群さんの経験談が盛り込まれた本です。幼少期の話が数多く語られ、よくもまあここまで覚えているものだ。と感心していると、読んでいくうちに自分にもそんな感情を抱いていた時があったなとハッとします。”私の心の拠りどころ”をこの本を通じて再確認できた気がします。たまに自分を振り返るとその存在に自然と感謝の気持ちが湧いてくるのは年をとった証拠でしょうか。軽快でちょっと刺激のある文体の中に大切なことをさらっと思い出させてくれる群さんの本をこれからも読み続けると思います。(読んでみたいなと思う本は9冊目、15冊目、21冊目でした。)
・うしろむき夕食店 冬森 灯
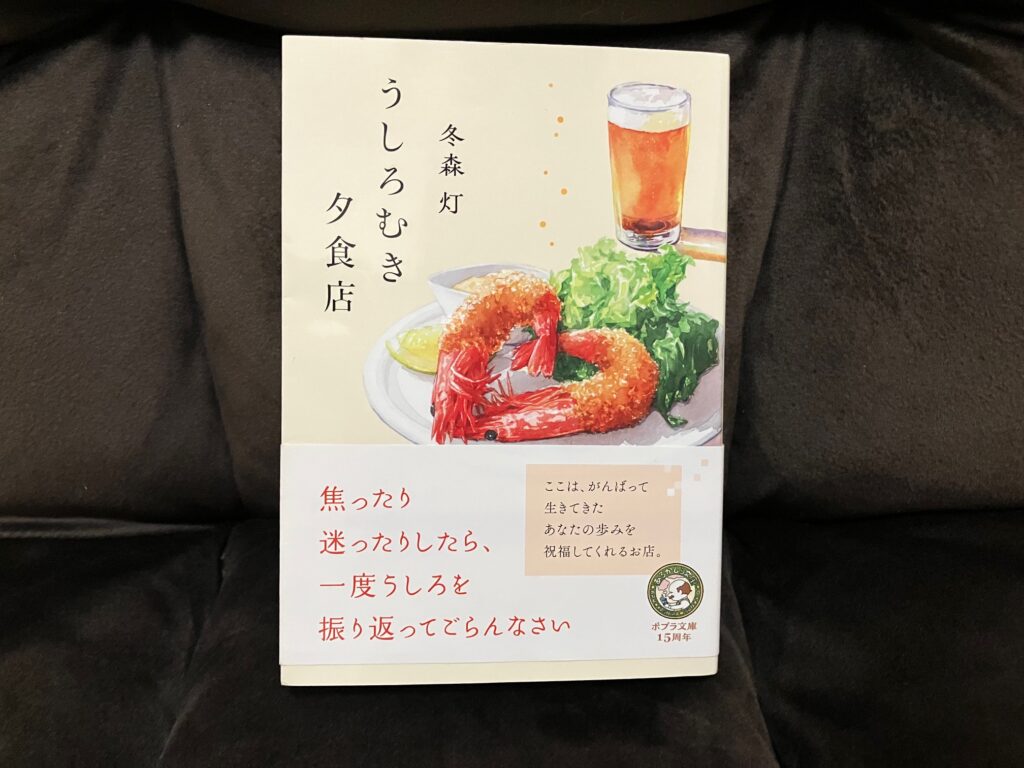
冬森さんは”縁結びカツサンド”で知り、ほっこりする読後感から気になっていた作家さんです。今回は題名に惹かれて購入。”うしろむき”という題名ですが、前向きになれる本。物語は5つのメニュー(章)で構成され、会社でも、自営業でも、家庭でも人との関わり方は千差万別で、それぞれの悩みを抱えた主人公たち。初心に返る出来事をきっかけに自分を振り返ることで、心にあるわだかまりを解消してくれるお話です。この本も作者らしい、ほっこり温まるような気持ちが広がります。なぜ、”うしろむき”夕食店なのかは読んでみてからのお楽しみです。
・こころの処方箋 河合 隼雄
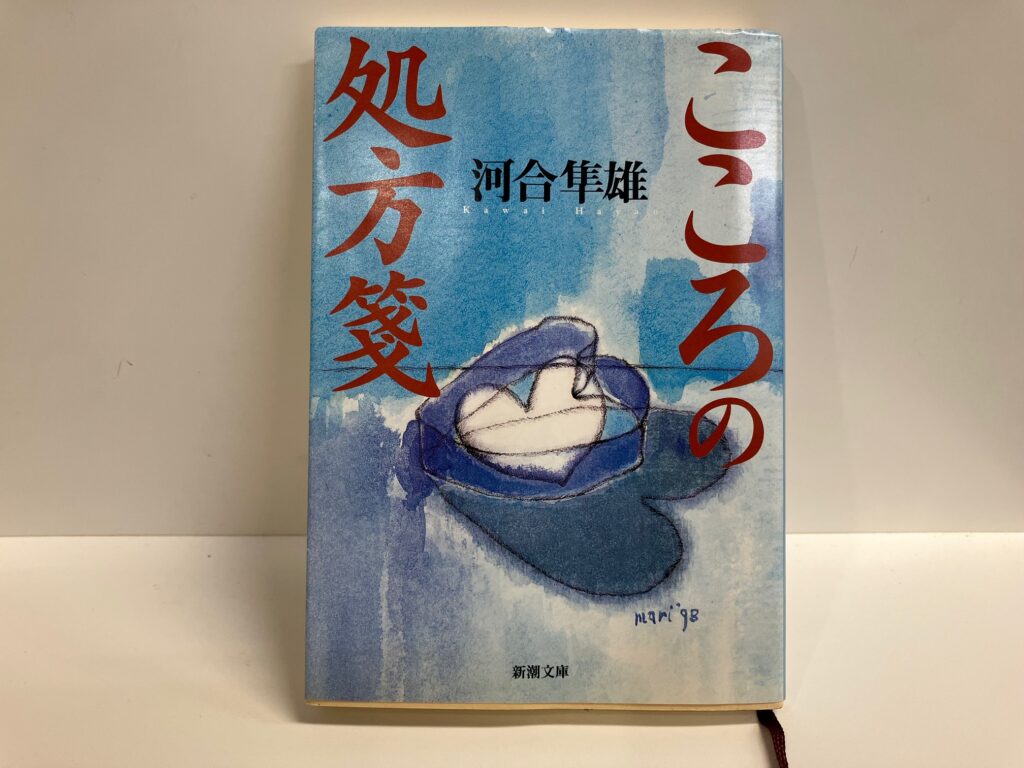
心理学者でありカウンセラーの著者が書いたこの本は、”処方箋”といっても”治す”ではなく、”対策”を”常識”という観点から語ってくれている気がします。何となく共通の認識としてわかってはいるものの、いざ言葉にするのは難しいのが”常識”。その難しいところを文章にしてくれているのが本書です。あとがきに書かれていましたが、
『常識とは家庭や地域内で、人から人へと伝わるものである。その機会があまりにも減少し、また、常識を伝える人たちの常識に対する自信の喪失ということもあって、子どもたちは常識を身に着ける機会を失ってしまったのだ。』 ――― あとがき p230
人とのコミュニケーションを取るとき、常識の共通認識が物事を円滑にすすめる1つの方法だったのかもしれません。メールやSNSなどの普及で格段に便利になった反面、以前よりも人との関りが希薄に感じられるようになったのは共通認識を確認し合う場が減ってしまったからでしょうか。そんなことを考えます。
・医師と侍 二宮 陸男
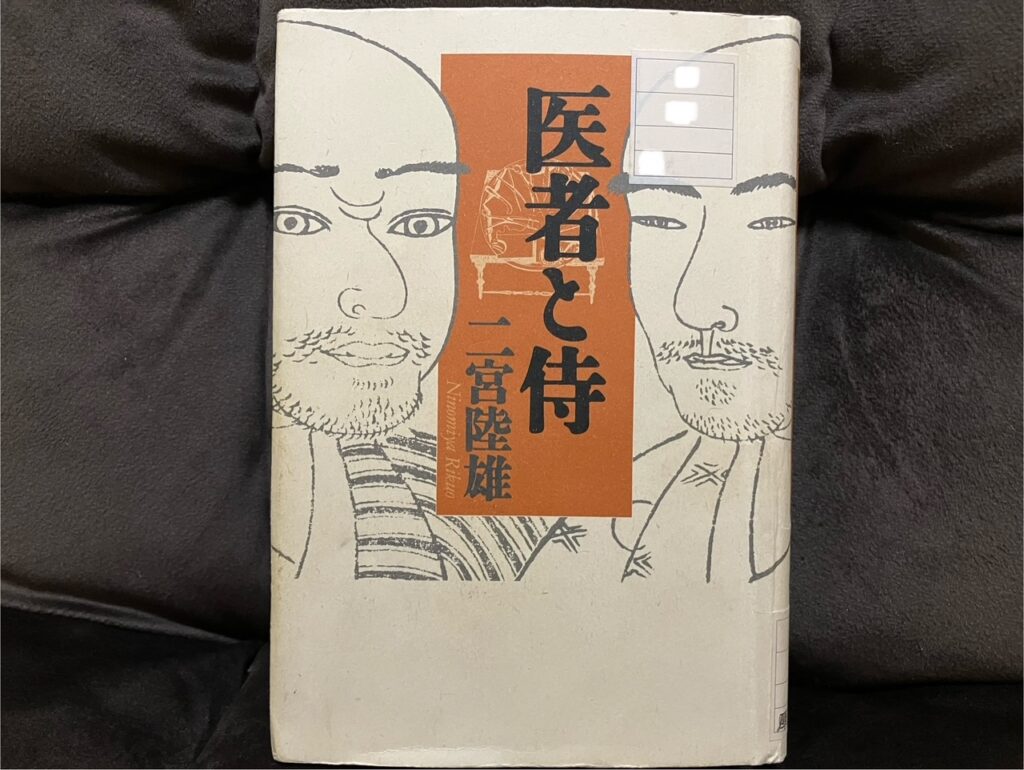
大河ドラマ”べらぼう”で、松前藩と蝦夷地の話があったころ。蝦夷地や松前藩に関わる史実を探していたときに見つけた本。この本の舞台は蝦夷地と津軽藩(現・青森県)です。そして壊血病により東北諸藩の多くの藩士が蝦夷地での越冬中に病死した過酷で悲惨な事件が題材になっています。蝦夷地はロシアとの攻防が続き、近隣の藩が警衛のために蝦夷地での越冬を命じられていた実際の史料が現存しています。壊血病は”ビタミンC欠乏症”のこと。今では原因も症状も分かりますが、病因に対する考えが浅かった時代には奇病として恐れられていました。原因不明の病と極寒の地で命を落とした藩士、その様子を見つめ生き残った藩士の無念さと緊張の描写に息をのむ思いで読んでいました。
史実の多くは歴史に埋もれたまま。史料を目にすることは難しくとも、小説で知ることは一つの勉強になるかと。(もちろんマンガでも!)今、こうして日本の事件や史実を知ろうとすると、歴史の授業は江戸後期から近代にかけて丁寧に教えて欲しかったなとつらつら思います。
________________________________________
今年の”神田古本まつり”の開催が決定しました!来月10月24日~11月3日までの期間で行われるようです。9月に入ってからバタバタしている状況が続く中、立ち寄る時間はあるのだろうか・・・毎年「行きたいな。」と言っている気がしています。
M


