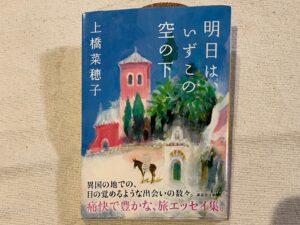今年は早くも花粉症の症状が出ている方がいらっしゃるようで、我が家は私の他に花粉症が1人いるのですが1月半ば頃から症状が出始めているそうです。今年の花粉は早く終わるのでしょうか、それとも長引くのでしょうか・・・。
花粉症と言えば思いつくのが、こちら。ーーー『小青竜湯(しょうせいりゅうとう)』

効能効果:体力中等度またはやや虚弱で、うすい水様の痰を伴う咳や鼻水が出るものの次の諸症:気管支炎、気管支喘息、鼻炎、アレルギー性鼻炎、浮腫み、感冒、花粉症
構成生薬:マオウ、シャクヤク、カンキョウ、カンゾウ、ケイヒ、サイシン、ゴミシ、ハンゲ
効能効果に、”花粉症”の記載があります。体表から体内まで温める効能や水分を取り除く効能のある生薬が多く含まれています。ポイントは胸の辺りに籠った”冷え”と”水毒”です。
特徴として、マオウ・ケイヒ・サイシンは辛温解表薬、カンキョウは温裏祛寒薬(大熱薬)、ハンゲは温化寒痰薬に分類されています。(漢薬の臨床応用より) 文字通り、”温薬”の効果をもった生薬が多いことが分かります。
全体的に温める処方なので、熱感や炎症のある場合や黄色い鼻水や痰には不向き。その場合は辛夷清肺湯や荊芥連翹湯などを使ってみてください。鼻水や痰が出にくい場合は、排膿散を併用してもいいかもしれません。
鼻水で良く用いられる『小青竜湯』ですが、サイシンには鎮咳作用があり、更にゴミシとカンキョウを組み合わせると「痰飲による咳嗽の良薬」として知られています。それにより気管支喘息や咳に対しても効果があります。
ここに”口渇”の症状があった場合は、『小青竜湯加石膏』という処方の方がよりよい効果が期待できます。
小青竜湯の”青竜”はマオウのことで、加工した際に青さが際立つからだそう。(私には黄緑色にしか見えないのですが)

※マオウ製剤は循環器系の既往や、高血圧の方や前立腺肥大症の方は少量の服用から始めることをおすすめします。※
昨年2月のブログでは、『麻黄附子細辛湯』をご紹介しました。合わせて参考にしてください。
【余談】
寒くなると盛大なくしゃみをし、鼻をかんでいるTさんにお願いをして効果の出方を試してもらうことにしました。
①小青竜湯のみ ②小青竜湯の増量 ③小青竜湯合麻黄附子細辛湯 (今回は三和生薬のエキス剤を使用しています。)
まずは①から。くしゃみ・鼻水の頻度は減ったのですが、ティッシュの消費はまだまだ多い。効果はあったので冷えがありそう。
続いて②に変更するも、症状は横ばい。
最後に③を試してみると、見違えるような改善に至りました。
どうやら典型的な”冷え”と”水毒”だったようです。そして、”冷え”がかなり強かったため、ブシの力が必要だったのでしょう。本人は花粉症ではないのですが、寒暖差によるアレルギー性鼻炎にも効果が期待できそうです。
※承諾を得て服用してもらっています。同じような症状でも薬の効き方には個人差があるので、必ず薬剤師や登録販売員にご相談の上服用して下さい※
今週は全国的に今季最大級の寒波に見舞われ、日本海側ではあっという間に大雪になってしまいました。千葉も風が強く寒いとはいえ、今までが少し異常な暖かさだったような。2月下旬頃からは暖かくなってくるようなので、身体も次第に活動的になってきます。それによって、冬の間に溜まったものが出てくる季節になります。これからの時期は食養生として、山菜や香菜を取り入れると解毒の手助けをしてくれるのでおすすめです。

(↑「豆狸」のおいなりさん)
昨日6日は、初午でした。五穀豊穣を願って稲荷神社では油揚げやお稲荷さんを見かけます。神様の使いとされる狐の好物と言われているためです。俵型は東日本、三角形は西日本で多く見られるそうです。
M